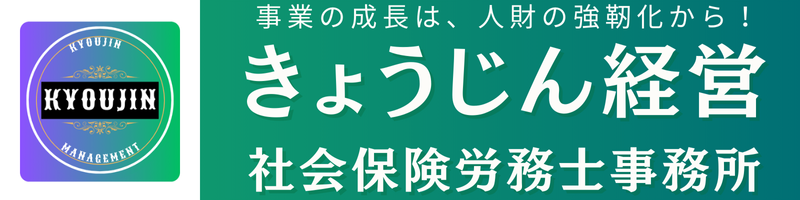今回の勉強会は「営業秘密管理」の重要性とその実践的な制度運用について解説した内容でした。特に技術情報や顧客情報を扱う企業においては、秘密管理の徹底が事業の根幹を支える要素であり、単なるモデル規程のコピーではなく、自社の実情に即した就業規則や別途「秘密管理規程」を整備することが求められます。
これには秘密保持義務、競業避止義務、違反時の懲戒規定などを明確化し、従業員への周知を徹底することが不可欠です。
また、退職者等による情報持ち出し問題では、不正競争防止法(不競法)が適用される場合が多く、裁判例では①有用性、②非公知性、③秘密管理性の3要件を満たした情報のみが営業秘密として保護されます。
具体例として紹介されたさいたま地裁の令和3年判決では、中古のパチンコ・スロット液晶パネルの仕入先情報を営業秘密として管理していた企業Xが、退職前に情報を持ち出し独立起業した元社員Y1に対して損害賠償を請求。裁判では不競法違反および秘密保持義務違反は認められたものの、競業避止義務違反は、期間が2年と長期で地域限定がなく、職業選択の自由を不当に制限するとして無効とされました。賠償額は当初請求の3,000万円から一審で約160万円、控訴審で30万円に減額され、情報の価値や使用実態が慎重に判断されることがわかります。
制度構築においては、秘密情報の定義、対象従業員の範囲、管理方法、義務の期間・地域、違反時の対応を明文化し、定期的な研修や周知徹底を行うことが推奨されます。
特に競業避止義務は半年から1年程度が実務上の相場とされ、副業・兼業の原則容認の流れとの整合も重要です。
参考資料として、経済産業省や中小企業庁のガイドラインも活用できます。